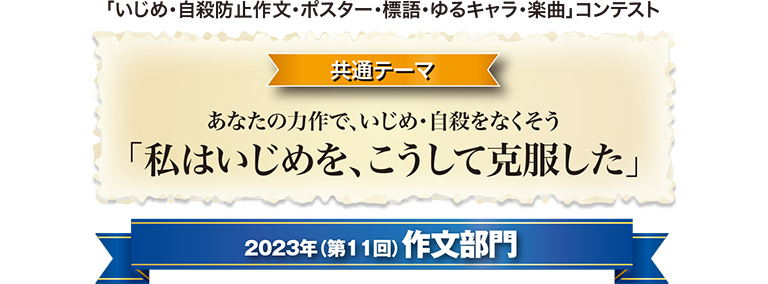プラスチックの塊が、床に叩きつけられる音がした。
背後で何が起きているかなんて、振り返らなくてもわかる。中学生になったわたしのために、母が四時半に起きて作ってくれたお弁当のおかずが、木タイルの床に散らばっているのだ。
「灯里の好きなの、入れておいたから」
今朝、母はそう言って微笑みながら黄色の弁当包みを手渡してくれた。母の手にはあかぎれが目立っていた。秋のはじめとはいえ、朝の冷たい水は滲みたにちがいない。
「ありがとう、うれしい」わたしは答えた。きっと、アスパラガスの肉巻きだ。わたしの大好物。でも、わたしがそれを食べることはできないかもしれないと、テレビの情報番組をぼんやりと眺めながら予感した。
最近、昼休みになると寄ってくる嫌なやつらがいる。
いわゆるいじめっ子で、彼らはわざわざわたしの食事の機会を奪いに来るのだ。ニキビだらけの高木という男子の顔は醜い。これが“いじめ”と呼ばれるものなら、彼がその主犯格だ。実際には彼の指示で、彼の取り巻きがわたしのお弁当をひっくり返したり、体育着を窓から投げ捨てたり、あるいは「ブス」とか「ドモリ」とか、わたしを傷つけようという悪意に満ちた言葉を投げつける。
いじめは、初めてのことではなかった。
小学校では二回転校して、その度に今と同じような目にあった。先生は、たまに現場に出くわすと彼らを怒鳴り、指導室に連れていくが、その後状況が好転したことは一度もない。
わたしは、人よりも話すスピードが遅く、発言しようとすればつかえてしまう。いわゆる吃音症と呼ばれるものらしかった。子どもは、「ちがうもの」に敏感だと思う。発表の場ではその特徴を笑われ、転校生という立場もあって、「ちょっとちがう子」の居場所はほとんどなかった。
「いずれ良くなりますから」とお医者さんは優しく言うけれど、良くなる日がいつなのかは、いつも教えてくれなかった。
「汚ねえ、さっさと拾えよ!」
高木が、勝ち誇った顔でわたしを見下し、命令する。
「散らかってんだろ、早くこれに入れて食えよ、ブタあ」
高木が弁当箱をわたしに投げつける。サラダのドレッシングが、わたしのスカートを汚した。取り巻きの松下と小原が笑う。こういう時、助けてくれるクラスメイトはいない。皆、何も起きていないみたいに黙々と自分の弁当を抱えて食べている。
嫌な言葉を吐かれるのには慣れたけど、わたしはこの瞬間だけはたまらなく嫌だった。無視されたり、暴言を吐かれたり、乱暴をされて傷つくのは、結局のところわたしひとりだ。でも、お弁当をひっくり返すのはそうじゃない。それは、わたしのお母さんを傷つける行為だ。
今、目の前の男子生徒は、母の心を踏み躙っている。
遅くまで働き疲れている母が、朝早くから指先の痛みに耐えながら、わたしのために作ってくれたお弁当。高木が放った弁当箱も、わたしの好きなキャラクターがいいと、家から離れたホームセンターまで一緒に探しにいってくれたものだ。自分が傷つけられるのは、我慢すれば済む。でも、ここにいないわたしの大切な人を傷つけることは、どうしても、許せなかった。
次第に高木が踏みつけている弁当箱の蓋が、母の手のひらのように思えた。そう思った途端、わたしの中に明らかに暴力的な気持ちが込み上げてきた。マグマのような熱量をもった怒りを必死に抑えようと努めたが、うまくはいかなかった。わたしは弁当箱を拾い上げて両手で握りしめ、高木のニキビだらけの醜い顔を、力を込めて、思い切り殴った。
目を覚ましたとき、保健室にいたのはわたしひとりだった。
きなり色のカーテンの向こうから、僅かに雨の音が聞こえる。高木の姿も、松下や小原の姿もない。とても静かだ。
保健室の櫻井先生が戻ってきた。
「慣れない興奮のせいで、気を失ってしまったみたいね。お母さまが迎えに来てくれるから、安心して休んでいて」
櫻井先生は、そう言って窓際のマリーゴールドに水を遣った。
「殴ったのは、わたしなんです」
わたしは櫻井先生に言った。
「そうみたいね。でも、痛い思いをしたのは、どっちかしら」
櫻井先生が答えた。
「あの子は佐竹先生にこってりやられてると思うわ。あの後、クラスの子が一部始終を佐竹先生に話してくれたんだって。だから、みんなわかってる。女の子をいじめるなんて、最低ね。一応“暴力事件”の加害者だから、佐竹先生、高木くんのお父さんの職場まで電話して、すぐ来てもらうことにしたってさ」
高木も松下も、母親がいない。高木の母親は離婚して出て行き、松下の母親は松下が幼稚園に入ってまもなく感染症で亡くなった。
「ねえ、先生ひとりごと言ってもいい?」
櫻井先生がわたしのベッドの端に腰をかけ、穏やかな声でそう尋ね、わたしは頷いた。
「人と違うものを持っていると、羨ましがられるものよね。自分には絶対手に入らないものを当たり前に持っている人を毎日見るのって、ひょっとしたら辛いことなのかも」
わたしは櫻井先生のひとりごとを聞いた。
「だから意地悪したくなっちゃうの。そういう人が幸せそうだと、自分は無価値に思えて辛いから。だから何とかして、自分だって価値があるんだぞって、証明しなきゃいけない気になってくるのよ。たとえば、大事な物を壊して困らせてやろうとか。痛めつけてやろうとか。そういうことで、バランスを取ろうとするの」
はい、とわたしは思わず返事をした。
「私も高校のときいじめられてたんだ。ひどかったのよ。暴言や乱暴なんて当たり前で、通学用の自転車を川に捨てられたりとか、髪の毛にさ、文化祭で使うペンキをかけられたりとか。ひどいでしょ。ははは」
櫻井先生、どうして笑えるんですか?
「え?ああ。昔は泣いてたよ。学校も退学したいって、親に泣きついたこともあったな。こんな人生が続くなら、もう死んじゃいたいって思った。部屋のペン立てにカッターナイフがあってね、これで手首をすうっと切ったら、もう悲しくないかな、なんて思ったり」
「でもね!ある時気づいたの。こんな状態が一生続くことなんて、まずあり得ないって。だって、学校って三年間でしょう?三年経てばいやでも卒業よ。それに女の子に嫌がらせするやつなんて、今は先生に叱られるだけでも、卒業したら逮捕されてもうおしまい。ちょっと大袈裟だけど、そう考えたら、すごく楽になったの。私は、なにかを奪われた気になっていたけど、本当はなにも奪われてなんかいなかった。つまりね、どんないじめっ子にも、どんな怖い人にも、絶対に、私から奪えないものがあるって、気づいたの」
それって、なんですか。わたしは尋ねた。
「頭のなかにあるもの。どう思うか、誰を大事にするか、何が好きで、何が嫌いか。そういうことは、たとえ人にどんなことをされても、決められるのは自分だけ」
久しぶりに先生らしいこと言ったかも、と櫻井先生は得意そうに立ち上がり、中庭へ続く勝手口の戸を開けた。雨は止んだようだった。
「あ、あの黄色いフォルクスワーゲン、三崎さんのお母さまじゃない?」
ベッドの上から母の車を認め、わたしは上履きを履いた。これから母と担任との三者面談が始まるだろう。カバンを持って保健室から出ようとすると、櫻井先生のやわらかい手のひらが、わたしの肩に触れた。
「そういうのは、今日じゃなくてもいいでしょう。ほら、ここから抜けて、もう帰っちゃいなさい。風邪でもないのに平日の午後に遊べるなんて、贅沢だぞ~」
悪戯っぽい笑みを浮かべる櫻井先生に唆され、わたしは教師に無断で学校を後にした。
車に乗ると、母は「おかえり」とだけ言って微笑んだ。油断すると、涙が溢れそうだった。
「お母さん、あのホームセンターに行きたい」とわたしは言った。母は「いいわよ」と、理由を聞かずに車を走らせた。
窓辺の景色を見て、わたしは素晴らしい午後だと思った。こんな気持ちは初めてだ。普段家に着くのは十七時ごろ。午後という時間を、わたしはほとんど知らなかったのだ。けれど、それはいつも確かにあった。雨上がりの大地の匂いがして、人々はゆっくり歩き、道路やお店はいつもより空いている。嫌なやつがいない、爽やかな世界。確かに存在するけれど、いつの間にか見えなくなってしまう世界があるということを、わたしは知った。
世界は、思っているよりもずっと広く、たくさんの人がいる。
高木みたいなやつもいれば、櫻井先生みたいな人もいる。彼女が言った「頭の中だけは誰にも侵せない」という言葉を、わたしは大切にしようと決めた。目の前の一部の出来事で、人生の全部を決めつけないように。誰かに痛めつけられて、自分の価値が下がったと絶望しないように。
わたしはわたしで、わたしたちの世界を守りたい。そう思った。
ホームセンターの移動販売車でソフトクリームを二つ買い、母と食べた。
十三歳のわたしにとって、ソフトクリームはいつもおいしいけれど、今日はミルクの甘さのなかに、少しだけ塩気を感じた。
「灯里、見て!」
母が指差す先には、大きな虹の橋が架かっていた。
これは、頭のなかに大切にしまっておこう。
わたしは、そう決意した。
|